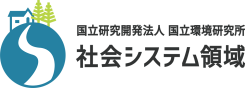2019年にスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリさんが世界の注目を集めたのに前後して、日本でも気候変動対策の強化を求めて声を上げる若者が出てきました。世間からは「社会の複雑さがわかっていない」と揶揄されたり、「意識が高い」と敬遠されたりすることも多い彼らですが、僕は彼らの存在を圧倒的に支持しています。
最近流行りの概念である「トランスフォーメーション」の観点から、その理由を説明します。
社会の「トランスフォーメーション」と将来世代
—声を上げる若者を僕が支持するワケ
この記事のポイント
・社会のトランスフォーメーションとは、社会の仕組みがすっかり変わること
・過去の歴史の中で起きたいくつかのトランスフォーメーションにおいて、差別や被害を受けた当事者たちが声を上げることが必要不可欠な作用だった
・気候変動問題は現在世代から将来世代への無意識の差別を含んでおり、それを克服するトランスフォーメーションが起きるためには将来世代が声を上げる必要がある
1. 「トランスフォーメーション」ってなんだ?
トランスフォーメーション(transformation)という言葉をよく聞くようになりました。辞書的な意味は「trans(超える、横断する)」+「form(形)」で、端から端まで横断的に、すっかりと形を変えることです。ちょっと変えるのではなくて、すっかり変えること。たとえば、芋虫が蛹を経て蝶になるのはトランスフォーメーションです。乗り物などがロボットに変形する映画の「トランスフォーマー」を思い出してもよいですね。
最近おそらく一番よく聞くのが、デジタル技術でビジネスなどをすっかり変えるデジタル・トランスフォーメーション(DX)でしょう(英語ではTrans-をXと略す習慣があるようです)。これにならってか、気候変動を止めるために社会をすっかり変えることをグリーン・トランスフォーメーション(GX)と呼ぶことがあります(日本政府も使っています)。さらに広く、社会を持続可能なものにすっかり変えることをサステイナビリティ・トランスフォーメーション(SX)と呼んでいるのも見かけます。
2. トランスフォーメーション概念との出会い
僕が最初にトランスフォーメーションという言葉を意識したのは、2013年ごろに、地球規模の持続可能性に関する国際研究プラットフォーム「Future Earth」の立ち上げの議論の中で「Transformations towards Sustainability」(持続可能性へのトランスフォーメーション)という表現を見たときです。それはFuture Earthの3大テーマのうちの一つを表す重要な概念でした。
どういう意味だろうと思って検索していると、ドイツの気候変動に関する助言委員会(WBGU)の文書に、ほぼ同じタイトルのものを見つけました。そこには、「持続可能性へのトランスフォーメーションは、その変化の規模と影響の大きさにおいて、人類の歴史の中で新石器革命(農耕牧畜の開始)と産業革命に匹敵する」と書いてありました。僕はそれを見て「え、そんなでかい話をしているの?」と驚きました。
その後、2015年に採択された国連の持続可能な開発目標(SDGs)の文書のタイトルに「Transforming our world」と書かれていたのをはじめ、気が付けば気候変動問題や生物多様性問題の解決策を論じた文書などにも、必ずと言っていいほどトランスフォーメーションの必要性がうたわれているのを目にするようになりました。
3.社会のトランスフォーメーションについて学んでみた
社会科学分野におけるトランスフォーメーションの概念を環境問題の文脈で整理した論文1)によれば、トランスフォーメーションの定義は様々なものがありますが、共通した認識は「システムの本質的な属性の変更を伴うような変化の過程」といえます。社会のトランスフォーメーションの場合は、社会構造、権力構造、制度、インフラといったものに加えて、人々の習慣、ライフスタイル、そして世界観などが(それらすべてではないにしても)変更されます。
実際に起きた社会のトランスフォーメーションの例としては、この論文によれば産業革命のほかに、古代文明の崩壊や、最近のものではベルリンの壁の崩壊(東欧革命)、南アフリカのアパルトヘイト体制の崩壊、中東・北アフリカ地域の「アラブの春」などが当てはまるとされています。ここに挙げられた近年の例はどれもある種の「民主化革命」ですので、変化を求めて立ち上がった人たちが勝ち取ったものというイメージが湧きます。社会の中の3.5%以上の人が非暴力の抗議運動に参加すると、このような変化が成功してきた、という研究もあります。
ただし、一般的にいえば、社会のトランスフォーメーションは起こそうと思えば計画的に起こせるようなものではなく、意図的な行動も偶然の出来事も、長期的な変化も突発的な事件も、国内の事も国際的な事も含めて、様々な要因が作用して起こる(かもしれないし、起こらないかもしれない)と理解すべきもののようです。
南アフリカの民主化を例にとると、国内の抵抗運動や事件、政治的なプロセスのほかに、他国からの経済制裁の影響やインターネットの普及による情報環境の変化、東欧の民主化等による国際政治環境の変化などの様々な要因が作用して、数十年の過程を経てトランスフォーメーションが起きました。その過程では、変化を押しとどめようとする勢力の行動など、逆向きの要因も作用します。変化は、予測不能で、複雑で、雑然とした形で進んだのです。
4. 勝ち取られてきたトランスフォーメーション
このような理解に基づいて考えると、近代以降の人類の歴史の中で、おおむね世界的な規模で起きた、奴隷制の廃止、植民地主義の崩壊、女性の参政権獲得といった差別的な制度や文化の克服は、それぞれがトランスフォーメーションとみなせると思います(もちろんこれらの進展は国によっても違いがありますし、現在でも差別的な状況が残る部分もあるわけですが)。これらの事例では、以前は制度的・文化的に当然許されていた差別が、トランスフォーメーションを経て当然許されないものになるという、大きな「常識の変化」が起きたといえます。
僕はこういった歴史に実はあまり詳しくないので、より身近な例として、自分自身も経験したタバコの例をよくあげています。「不適切にもほどがある!」というドラマ(TBS系2024年) でも描かれたようですが、昭和の時代は、交通機関でも飲食店でも職場でも、どこでもタバコを吸えるのが当たり前でした。それがトランスフォーメーションを経て、現在では当然許されないものになるという「常識の変化」が起きています。
これらのトランスフォーメーションも、偶然を含む様々な出来事や状況の変化が複雑に作用して、変化を押しとどめようとする作用と変化を進めようとする作用とが何度ももみ合いながら、雑然とした過程を経て起きたのだと思います。しかし、変化を進める方向の重要な作用として、差別的な扱いや被害を受けている当事者たちが立ち上がって、変化を求めて声を上げることが必要不可欠だったに違いありません(タバコの例でも、受動喫煙の被害者が「嫌煙権訴訟」などの形で声を上げました)。やはりこれらの事例は、当事者たちによって「勝ち取られてきた」側面を持つのだと思います。
5. 声を上げる将来世代の出現
気候変動問題やその他の世代間問題において将来世代が置かれているのは、奴隷や、植民地や、参政権を持たない女性に相当するような、差別的な状況と考えることができます。現在世代が排出する温室効果ガスによって将来の気候変動がさらに進行することは確実です。それによって深刻な悪影響が出た地球の上で生きていくのは将来世代なわけですが、気候変動にどのように対処するかは、ほとんど現在世代が決めてしまっています。
この状況を変えたいと思っても、これから生まれてくる将来世代は、当然、声を上げることができません。声を上げることができるのは、既に生まれている将来世代、つまり子供から若者です。将来世代の差別的状況を克服するトランスフォーメーションのプロセスが始動するためには、言ってみれば「子供の反乱」が起きる必要がありました。残念ながらそんなことは起きないだろう、と僕は考えていました。2018年の12月に、ある動画を見るまでは。
その動画を見たときの衝撃は今でも忘れられません。オーストラリアで大勢の子供たちが学校を休んで気候変動対策の強化を訴える抗議行動を行っている映像です。そのような抗議行動がいくつかの国で起き始めており、その引き金になったのが当時15歳のスウェーデンの一人の少女であったことは後から知りました。その少女、グレタ・トゥーンベリさんが2019年9月の国連のスピーチで世界中に知られるようになったのはご存じのとおりです。
6. 声を上げる若者を僕が支持するワケ
ついに「子供の反乱」が起きた、と僕は思いました。そして2019年には、日本でも気候変動対策を求めて声を上げる若者が、少数とはいえ現れ始めました。僕は彼らに興味を持ち、彼らの何人かと話す機会を持ち、一人の気候科学者として機会があれば彼らに協力するようにしてきました。
彼らは、特に日本では、若者の中でも圧倒的に少数派です。批判されたと感じた大人に反発されることも、同世代に「意識が高い」と距離を置かれることも、少なくありません。彼らの多くは、平均的な同世代に比べて気候変動問題への感受性が強く、将来の世界への気候変動の影響が心配であるだけでなく、自分を含めた先進国の人々が主に引き起こした気候変動で、途上国などの脆弱な状況にある人々が最も苦しんでいるという自分自身の加害者性や特権性に胸を痛めています。これは、彼らの個性なのだと思います。
現在世代が無意識に将来世代を差別していること、つまり現在世代が勝手に決めた不十分な気候変動対策が将来世代の人権を侵害していることの認識は、今の社会ではほとんど共有されていません。この認識が当然のものとして共有されるような「常識の変化」に至るまでのトランスフォーメーションが完遂することを僕は望みます。そのためには、彼らのような若者が声を上げ続けることと、彼らを支持する現在世代が増えていくことが必要不可欠なのだと思います。これが、僕が声を上げる若者を支持する理由です。
博士(学術)。もともとは気候変動の将来予測の研究者。今は日本で一番気候変動の解説がわかりやすいおじさんを名乗っています。2024年3月に27年勤めた国立環境研究所を退職して大学に完全に移りました。学生とも議論しながら、気候変動の科学と社会の諸問題について考えていきたいです。
記事へのご意見やご感想をお聞かせください。執筆者からの質問にも答えていただけると嬉しいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。ご意見などをからお寄せ下さい。
今回の執筆者から皆様への質問:現在の常識で、30年後にはすっかり変わっていてほしいことは何ですか?
参考文献
1)Brown, K., S. O’Neill, and C. Fabricius. 2013. Social science understandings of transformation. Pages 100-107 in ISSC and UNESCO. World Social Science Report 2013, Changing Global Environments. OECD Publishing and UNESCO Publishing, Paris.