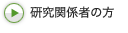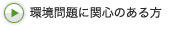愛知目標の次のステージへ向けて:
「昆明・モントリオール生物多様性枠組」について特集しました
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)
掲載論文は以下の通りです。 1)昆明・モントリオール生物多様性枠組及びその議論過程 2)昆明・モントリオール生物多様性枠組の目標・ターゲット・指標:その内容と有用性の解説 3)昆明・モントリオールグローバル生物多様性枠組における資源動員と主流化:情報開示の役割と気候変動との類似性 4)昆明・モントリオール生物多様性枠組の実施に向けた新たなPDCAサイクルと我が国への影響について
1. 特集の経緯と目的
昆明・モントリオール生物多様性枠組には、2030年までに世界の陸と海の30%を保全する「30by30」目標など、生態系保全と資源の持続可能な利用に関する具体的な目標が含まれています。目標には、モニタリングや資金(資源)動員、民間部門との協働、遺伝情報の利用から得られる利益の配分といった様々な項目があり、カバーする範囲は広く、その内容も複雑です。そのため、目標の全容を把握することは容易ではありません。国立環境研究所は、これらの重要かつ複雑な情報をより多くの方にわかりやすくお伝えするため、特集の発起人として企画を行いました。
この特集号には、国立環境研究所をはじめ、電力中央研究所、東京大学、東京都立大学、ロンドン大学、長崎大学、一般社団法人海外環境協力センターなど、多様な組織に属する専門家が寄稿しています。また、執筆者には、2022年に開催されたCBD COP15や、その事前会合である生物多様性条約科学技術助言補助機関会合(SBSTTA)、ポスト2020生物多様性枠組公開作業部会(OEWG)、特別技術専門家部会(AHTEG)に参加していた研究者や交渉関係者が含まれています。各論文では、現場での経験と知見に基づいた解説と将来展望を説明しており、生物多様性保全に関係する多くの方々に役立つ情報を提供できると考えています。
2. 掲載論文
(1)
昆明・モントリオール生物多様性枠組及びその議論過程
大澤隆文1*・香坂玲2(*:責任著者)
1 東京都立大学都市環境科学研究科
2 東京大学大学院農学生命科学研究科
本稿では、近年、国際的な目標設定において注目されるSMART(Specific/Measurable/Ambitious/Realistic/Time-bound)の観点から、2010年に合意された「生物多様性戦略計画2011-2020 及び愛知目標」と、その後継目標となる「KMGBF(Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework)」を比較しています。この比較を通じて、KMGBFの特徴を明らかにし、資源動員、遺伝情報の利用から得られる利益配分に係る議論の経緯や関係性を整理しました。また、KMGBF実施における今後の課題と展望を生態学と社会経済的な見地から考察しています。
リンク:https://doi.org/10.18960/seitai.74.1_71(外部サイトに接続します)
DOI:10.18960/seitai.74.1_71(外部サイトに接続します)
(2)
昆明・モントリオール生物多様性枠組の目標・ターゲット・指標:その内容と有用性の解説
池上真木彦1*・角真耶1・石田孝英1・山野博哉1・香坂玲2・石濱史子1・亀山哲1・小出大1・小林邦彦3・富田基史4・角谷拓1(*:責任著者)
1 国立研究開発法人国立環境研究所 生物多様性領域
2 東京大学大学院農学生命科学研究科 森林科学専攻
3 一般社団法人海外環境協力センター
4 一般財団法人電力中央研究所
KMGBFは30by30などの野心的な数値目標を含み、先住民や女性への配慮を含む4つの包括的なゴールと23のターゲットで構成されています。また、各ターゲットにおける達成への進捗状況を客観的に測定できる様々な指標が設けられています。その一方で、ターゲットの数は愛知目標よりも増加し、文章も長く複雑となり、ターゲット間での重複要素も含まれるため、各指標を含めてその全容を把握するのは容易ではありません。そこで本稿では、これらの目標、ターゲット、指標を解説し、KMGBF 目標達成のための国内外の動向と必要な行動を考察しています。
リンク:https://doi.org/10.18960/seitai.74.1_85(外部サイトに接続します)
DOI:10.18960/seitai.74.1_85(外部サイトに接続します)
(3)
昆明・モントリオールグローバル生物多様性枠組における資源動員と主流化:情報開示の役割と気候変動との類似性
富田基史1*(*:責任著者)
1 一般財団法人電力中央研究所
生物多様性の保全には資金が必要ですが、先進国・発展途上国を問わず、十分な資金の確保は容易ではありません。本稿では、KMGBFのなかでも、資金確保に関連する要素である資源動員と主流化という目標に焦点を当て、各目標の内容と愛知目標からの経緯を解説しています。資源動員目標では、年間7,000 億ドルの資金ギャップを解消するため、有害な奨励措置の廃止とともに、新たな公的資金や民間資金の動員が掲げられています。資源動員の手段の一つである主流化に関しては、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)をはじめとする情報開示が、民間部門への主流化の手段として位置付けられています。気候変動分野では、企業による情報開示を契機として金融機関が排出削減のための資金供給を行う流れが形成されつつあり、この動向が生物多様性の保全に向けた資金供給の促進につながる可能性を指摘しています。
リンク:https://doi.org/10.18960/seitai.74.1_111(外部サイトに接続します)
DOI:10.18960/seitai.74.1_111(外部サイトに接続します)
(4)
昆明・モントリオール生物多様性枠組の実施に向けた新たなPDCA サイクルと我が国への影響について
友居洋暁1,2、石井颯杜3、大澤隆文4*(*:責任著者)
1 ロンドン大学衛生熱帯医学大学院
2 長崎大学熱帯医学・グローバルヘルス研究科
3 環境省自然環境局
4 東京都立大学都市環境科学研究科
KMGBFには、目標だけでなく、その達成に向けた取り組みの透明性を高めるメカニズムが含まれます。本稿では、強化された計画・モニタリング・報告・レビュー制度(PDCAサイクル)について概説し、その課題を整理しています。さらに、同制度が今後の我が国の国家戦略や施策の実施、および国内のステークホルダーに与えうる影響について考察しています。また、生態学を始めとする学術研究やデータが進捗状況のモニタリングに果たす役割、新たなPDCAサイクルを踏まえた学術領域と政策決定者の対話・連携の重要性についても論じています。
リンク:https://doi.org/10.18960/seitai.74.1_123(外部サイトに接続します)
DOI:10.18960/seitai.74.1_123(外部サイトに接続します)
3. 発表者
本報道発表の発表者は以下のとおりです。
国立環境研究所 生物多様性領域
琵琶湖分室 主任研究員 池上 真木彦
4. 問合せ先
【研究に関する問合せ】
国立環境研究所 生物多様性領域
琵琶湖分室 主任研究員 池上 真木彦
【報道に関する問合せ】
国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室
kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)