有機フッ素化合物等POPs様汚染物質の発生源評価・対策並びに汚染実態解明のための基盤技術開発に関する研究(特別研究)
平成15〜17年度
国立環境研究所特別研究報告 SR-67-2006
1 研究の背景と目的
PCBやダイオキシン類等の残留性有機汚染物質(POPs)への国際的な取り組みを規定するストックホルム条約には、新たな規制物質を追加する仕組みが備えられている。その追加候補として、意図的に作られる化学物質の中からパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)などの一連の有機フッ素系界面活性剤を、また非意図的生成物質の中から多環芳香族炭化水素(PAHs)を選び、それぞれに対して効果的な対策立案に資する基礎情報を提供できる研究基盤技術開発を進め、あわせて汚染実態調査を進めた。
2 報告書の要旨
課題1:POPs並びに類縁の有機フッ素系界面活性剤に関する研究
汚染実態の調査並びに分解・処理方法の基礎検討を行った。また、曝露評価に使える生物指標の探索を進めた。PFOS並びに炭素数8~12の一連のパーフルオロアルキルカルボン酸(PFCsと総称)の分析法を確立し、文献調査その他から主たる環境排出先と考えられた河川並びに沿岸環境の実態調査を進めるとともに、下水処理での挙動を明らかにした。生物(二枚貝)試料からPFCsを測定するには従来の抽出方法では不十分であることがわかり、強アルカリ処理に基づく新たな方法を確立して全国調査を行ったところ、大都市域沿岸のほか、いくつか濃度レベルの局所的に高い地域を見いだした(図1、図2)。それぞれの場所でのPFCsのパターンには違いがあり、これらが互いに用途が異なる様子が明らかとなった。河川のPFOS調査では、比較的少数の大口の発生源が見つかった。その一つの下水処理場で調査した結果、通常の下水処理ではPFOSの大半は処理できずに放流されていく様子が明らかとなった。また、流域調査では、PFOSとPFOAの主要な発生源が異なる様子も明らかになった。
実際の環境中での曝露評価の推進を目的として有機フッ素系界面活性剤への曝露にともない魚に特異的に誘導されるタンパク質(生物指標:Biomarker)の探索を進めた結果、nucleoside diphosphate kinaseとよばれる酵素あるいはその類縁タンパク質が見つかった。また、分解処理の可能性を検討するため、PFOSの紫外線分解処理について検討した。その結果、水中でも分解は進むこと、特に2-プロパノール中で促進されること、分解は炭素とフッ素及び炭素と硫黄との間でおき、最終的に硫酸イオンとフッ化物イオンができるほか、炭素同士の結合もランダムに切れて各種の低分子フルオロカーボン類が気相中に出て行く様子も明らかとなった。
課題2:放射性炭素14Cを用いた大気粉じん中炭素成分並びに多環芳香族炭化水素の発生源解明に関する研究
燃焼起源で意図せずに作られ環境大気中に放出される粉じんの炭素成分、とくにPAHsについては、その主な発生源を特定することが発生源対策上重要な課題となる。宇宙線起源放射性炭素14Cは、木や紙等のバイオマス製品に含まれる一方石油や軽油などの化石燃料には含まれないため、14Cを測定してその主な起源が化石燃料かどうかを定量的に判断できる。この原理を利用し、実際の環境大気中PAHsやその他の燃焼起源炭素の発生源の割合を明らかにするための手法開発に取り組んだ。燃焼起源炭素を主成分とする画分としては、1)大気粉じんのうち粒径1.1ミクロン以下のPM1.1、2)元素状炭素(EC;いわゆる煤)、3)大気中PAHsのうち環数が多い画分、があり、それぞれの14C濃度の測定法を開発、確立し、実試料を測定して相互に比較した。1)のPM1.1の14C測定は粒径別の捕集を行った後、巨大なフィルター上の微量の炭素成分中の14Cを測定するため大型の燃焼管を作成し、粉じん中炭素を二酸化炭素に燃焼する条件を確立した。2)においては炭素成分を有機炭素OCと元素状炭素ECに分離する条件の確立が重要である。有機溶媒抽出、加熱分離(無酸素)、加熱分離(酸素存在下)の3つの手法についてそれぞれ条件検討を行った結果、無酸素下800度加熱分離がもっともよい結果を与えた。さらに3)では微量のPAHsを14C測定が可能な量集めて精製し測定するという、技術的にきわめてチャレンジングな課題をクリアするために、これまで開発を行ってきた微量試料グラファイト化技術、微量試料測定技術と分取ガスクロマトグラフによる分離・精製技術を組み合わせ、東京近郊で2~数ヶ月単位で捕集した大気粉じん中のPAHs成分の精製、14C測定を行った。
道路沿道では9割前後或いはそれ以上が軽油などの化石燃料起源と考えられる結果となったが、東京都区内でも沿道を離れると燃焼起源炭素の3~4割程度がバイオマスから来ることがわかった。さらに田園地帯のつくばでは、ECの半分強がバイオマス起源となった。東京近郊で捕集したPAHsも、3割程度がバイオマス燃焼起源であることがわかった。その発生源の特定はまだできていないが、野焼きなどいくつかの起源が考えられる。以上の結果、日本におけるPAHsの効果的削減のためには、自動車等の化石燃料燃焼ばかりでなく、バイオマス燃焼起源の発生源の特定とその削減方策の立案も軽視できないことが明らかとなった。
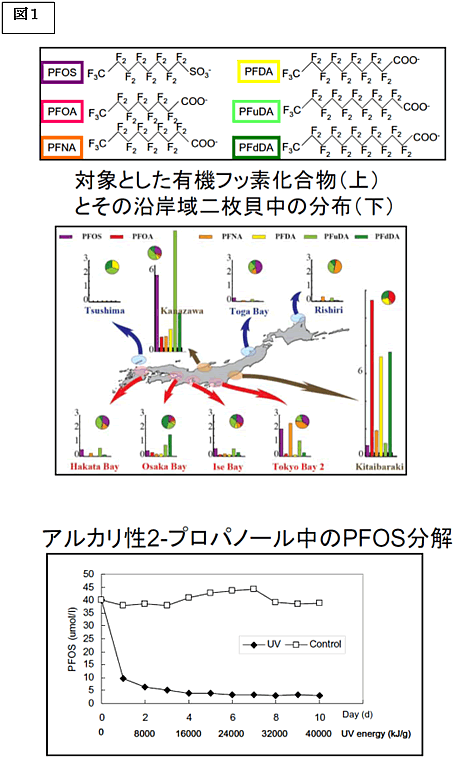
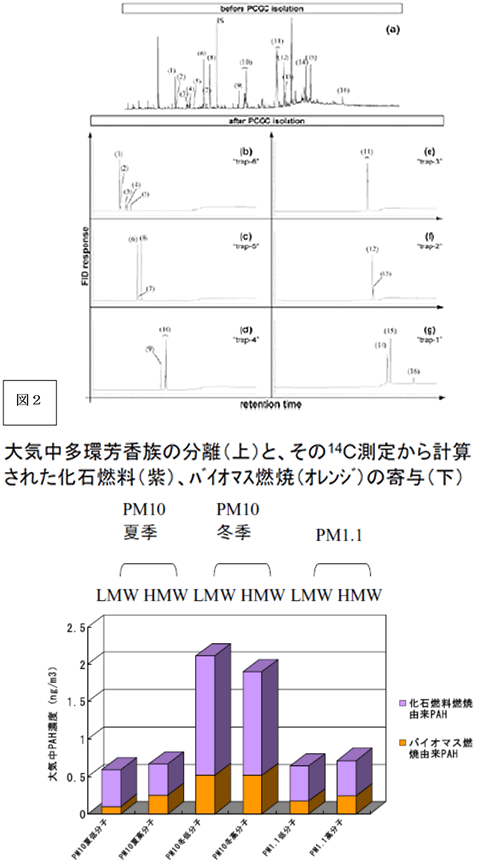
独立行政法人国立環境研究所
化学環境研究領域 柴田康行
Tel. 029-850-2450














