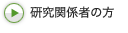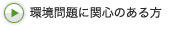2018年7月5日
「宇宙と地上から温室効果ガスを捉える-太陽光による高精度観測への挑戦-」
国立環境研究所「環境儀」第69号の刊行について(お知らせ)
(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ同時配付)
| 平成30年7月5日(木) 国立研究開発法人国立環境研究所 編集分科会委員長 :江守 正多 〃 担当WGリーダー:横畠 徳太 〃 事務局(環境情報部情報企画室) 室長 :阿部 裕明 担当 :青池美江子 |
国立研究開発法人国立環境研究所(以下、『国立環境研究所』という。)は、研究成果等をわかりやすく伝える研究情報誌「環境儀」の最新号、「宇宙と地上から温室効果ガスを捉える-太陽光による高精度観測への挑戦-」を刊行します。
国立環境研究所では、地球温暖化の現状把握と対策のために、離れた場所から物質の特徴を把握する「分光リモートセンシング」技術を用いた人工衛星による温室効果ガス観測プロジェクトを、宇宙航空研究開発機構(JAXA)・環境省と進めています。さらに各国との地上観測ネットワークを通じて、温室効果ガス観測のさらなる精度向上に取り組んでいます。
本号では、分光リモートセンシングによる温室効果ガスの観測について紹介します。
国立環境研究所では、地球温暖化の現状把握と対策のために、離れた場所から物質の特徴を把握する「分光リモートセンシング」技術を用いた人工衛星による温室効果ガス観測プロジェクトを、宇宙航空研究開発機構(JAXA)・環境省と進めています。さらに各国との地上観測ネットワークを通じて、温室効果ガス観測のさらなる精度向上に取り組んでいます。
本号では、分光リモートセンシングによる温室効果ガスの観測について紹介します。
1 本号の内容
○Interview 研究者に聞く「宇宙から温室効果ガスを観測する」
いぶき(GOSAT: Greenhouse gases Observing SATellite)は、2009年に打ち上げられた世界で初めての本格的な温室効果ガス観測衛星です。GOSATプロジェクトでは、この人工衛星を用いて、地球温暖化の原因とされている二酸化炭素やメタンガスを分光リモートセンシングという方法で宇宙から観測しています。本号では、プロジェクトの推進にあたっての数々の苦難や、温室効果ガス観測の高精度化への挑戦の取り組みを紹介します。
<研究担当者>
森野 勇(もりの いさむ)
地球環境研究センター 衛星観測研究室 主任研究員
地球環境研究センター 衛星観測研究室 主任研究員
吉田 幸生(よしだ ゆきお)
地球環境研究センター 衛星観測研究室 主任研究員
地球環境研究センター 衛星観測研究室 主任研究員
○Summary「分光リモートセンシングによる温室効果ガス観測の高精度化への挑戦」
いぶきで得られた初期データの解析結果は、高精度な地上データと比較すると、4%ほど値のズレがありました。分光リモートセンシングのデータは大きな場合は10%ぐらいの誤差があることが普通なので、分光リモートセンシングの精度としては悪くありません。しかし、このプロジェクトの目標ではより高精度な観測を行うことを目指していました。これがさらなる苦難と挑戦の始まりでした。
○研究をめぐって「分光リモートセンシングによる温室効果ガス観測」
分光リモートセンシングを用いた人工衛星と地上設置FTS観測網により、温室効果ガスの高精度な全球規模の観測が実現しました。日本のいぶきによるGOSATプロジェクトの成功と観測ネットワークの拡充により、温室効果ガスの分光リモートセンシングはますます発展しています。ここでは国内外の状況を紹介します。
2 閲覧・入手についての問い合わせ先
-
本号掲載URL
-
既刊「環境儀」掲載URL
-
国立環境研究所 環境情報部情報企画室出版普及係
TEL: 029-850-2343、E-mail: pub(末尾に@nies.go.jpをつけてください)
関連新着情報
-
2024年6月28日
 災害用備蓄食品をフードバンクへ提供(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)
災害用備蓄食品をフードバンクへ提供(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)
-
2024年5月29日
 気候変動下の極端高温による熱中症発生で救急車が足りなくなる(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)
気候変動下の極端高温による熱中症発生で救急車が足りなくなる(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)
-
2024年4月12日
 2022年度の我が国の温室効果ガス排出・吸収量について
2022年度の我が国の温室効果ガス排出・吸収量について
-
2024年3月7日
 「ココが知りたい地球温暖化」を更新しました -第二弾-
「ココが知りたい地球温暖化」を更新しました -第二弾-
-
2024年1月25日
 建築材料のカーボンニュートラル達成に必要な対策を解明 -木造化・国産材供給・再造林の同時推進が鍵に-(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)
建築材料のカーボンニュートラル達成に必要な対策を解明 -木造化・国産材供給・再造林の同時推進が鍵に-(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)
-
2023年12月19日
 「ココが知りたい地球温暖化」を更新しました -第一弾-
「ココが知りたい地球温暖化」を更新しました -第一弾-
-
2023年11月30日
 殺虫剤と水田の水温上昇がトンボ類に与える影響を解明
殺虫剤と水田の水温上昇がトンボ類に与える影響を解明
温暖化に起因する水温上昇は殺虫剤による生態リスクを高める可能性
(大阪科学・大学記者クラブ、農政クラブ、農林記者会、文部科学記者会、科学記者会、環境記者会、環境問題研究会、東大阪市政記者クラブ、奈良県政・経済記者クラブ、奈良県文化教育記者クラブ、筑波研究学園都市記者会、弘前記者会同時配付) -
2023年10月16日
 衛星が観測した植生クロロフィル蛍光データによる植生への干ばつ影響の検出
衛星が観測した植生クロロフィル蛍光データによる植生への干ばつ影響の検出
— GOSAT(「いぶき」)のデータから土壌乾燥が草本植生に与える影響を観測可能に —(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付) -
2023年9月26日
 冬季の湿原におけるメタン排出推定値の精度向上
冬季の湿原におけるメタン排出推定値の精度向上
湿原モデルは北方湿原からの冬季メタン放出量を過小評価していた(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付) -
2023年9月11日
 「いぶき」(GOSAT)と「いぶき2号」(GOSAT-2)の温室効果ガス濃度の整合性調査
「いぶき」(GOSAT)と「いぶき2号」(GOSAT-2)の温室効果ガス濃度の整合性調査
— GOSATシリーズによる温室効果ガス濃度の長期間データ整備の取り組み —(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付) -
2023年8月24日
 物質フロー指標の改善と温室効果ガス排出削減が両立しないサプライチェーンの要因を特定(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)
物質フロー指標の改善と温室効果ガス排出削減が両立しないサプライチェーンの要因を特定(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)
-
2023年7月7日
 「アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ第20回会合(WGIA20)」の結果について(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境問題研究会同時配布)
「アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ第20回会合(WGIA20)」の結果について(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境問題研究会同時配布)
-
2023年5月19日
 社会経済・技術の変革による脱炭素化費用の低減(京都大学記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会、北海道教育庁記者クラブ、筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会)
社会経済・技術の変革による脱炭素化費用の低減(京都大学記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会、北海道教育庁記者クラブ、筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会)
-
2023年4月27日
 気候予測データを機械学習により詳細化する技術の開発に成功(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)
気候予測データを機械学習により詳細化する技術の開発に成功(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)
-
2023年4月21日
 2021年度(令和3年度)の温室効果ガス排出・吸収量(確報値)について
2021年度(令和3年度)の温室効果ガス排出・吸収量(確報値)について
-
2023年4月18日
 「いぶき」(GOSAT)の温室効果ガス濃度推定手法の更新—衛星観測による温室効果ガス濃度の新たなデータセット—(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)
「いぶき」(GOSAT)の温室効果ガス濃度推定手法の更新—衛星観測による温室効果ガス濃度の新たなデータセット—(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)
-
2023年4月5日
 SII-8プロジェクトによる温室効果ガス収支レポート2023年版の公開について
SII-8プロジェクトによる温室効果ガス収支レポート2023年版の公開について
-
2023年1月17日
 オンラインイベント「観測とシミュレーションで読み解く『温室効果ガス収支』-”最良の科学”に向けて-」開催のご案内【終了しました】
オンラインイベント「観測とシミュレーションで読み解く『温室効果ガス収支』-”最良の科学”に向けて-」開催のご案内【終了しました】
-
2022年12月27日
 ミニチュア大洋「日本海」が発する警告
ミニチュア大洋「日本海」が発する警告
海洋環境への地球温暖化の影響
国立環境研究所『環境儀』第86号の刊行について(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ同時配付) -
2022年12月13日
 高山植物のお花畑、消失の危機
高山植物のお花畑、消失の危機
~大雪山国立公園における気候変動影響予測~(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、北海道庁道政記者クラブ同時配付) -
2022年11月28日
 衛星観測データのモデル解析により中国北東部におけるメタン漏洩が明らかになりました
衛星観測データのモデル解析により中国北東部におけるメタン漏洩が明らかになりました
~温室効果ガス観測技術衛星GOSAT(「いぶき」)の観測データによる研究成果~
-
2022年10月7日
 日本近海で増える極端昇温への
日本近海で増える極端昇温への
地球温暖化の影響が明らかに
~「1.5℃目標」達成で過去最高水温の常態化を回避~(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学記者会、科学記者会同時配付) -
2022年7月19日
 「アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ第19回会合(WGIA19)」
「アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ第19回会合(WGIA19)」
の結果について(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ同時配付) -
2022年6月28日
 近い将来に世界複数の地域で過去最大を超える干ばつが常態化することを予測
近い将来に世界複数の地域で過去最大を超える干ばつが常態化することを予測
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学記者会、科学記者会、大学記者会(東京大学)同時配付) -
2022年4月15日
 2020年度(令和2年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について(環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会 同時発表)
2020年度(令和2年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について(環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会 同時発表)
-
2022年4月15日
 「3Dふくしま」プロジェクションマッピングで環境研究を「触れる化」したい!国環研初クラウドファンディング挑戦のお知らせ(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、福島県政記者クラブ、郡山記者クラブ同時配付)
「3Dふくしま」プロジェクションマッピングで環境研究を「触れる化」したい!国環研初クラウドファンディング挑戦のお知らせ(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、福島県政記者クラブ、郡山記者クラブ同時配付)
-
2022年3月10日
 メタンの全大気平均濃度の2021年の年増加量が
メタンの全大気平均濃度の2021年の年増加量が
2011年以降で最大になりました
~温室効果ガス観測技術衛星GOSAT(「いぶき」)の
観測データより~(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付) -
2022年2月24日
 21世紀後半までの降水量変化予測の不確実性を
21世紀後半までの降水量変化予測の不確実性を
低減することに初めて成功しました(文部科学記者会、科学記者会、大学記者会、筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付) -
2022年2月4日
 こおりやま広域連携中枢都市圏
こおりやま広域連携中枢都市圏
公民協奏パートナーシップ包括連携協定
の締結について(お知らせ)(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、福島県政記者クラブ、郡山記者クラブ同時配付) -
2021年12月16日
 中国から排出されるブラックカーボンの主要起源は「家庭」 COVID-19・パンデミック期の排出バランス変化を利用した観測データ解析から(文部科学記者会、科学記者会、神奈川県政記者クラブ、横須賀市政記者クラブ、青森県政記者会、むつ市政記者会、高知県政記者クラブ、沖縄県政記者クラブ、名護市駐在3社、兵庫県教育委員会記者クラブ、神戸民放記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ、環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会、立川市政記者クラブ同時配付)
中国から排出されるブラックカーボンの主要起源は「家庭」 COVID-19・パンデミック期の排出バランス変化を利用した観測データ解析から(文部科学記者会、科学記者会、神奈川県政記者クラブ、横須賀市政記者クラブ、青森県政記者会、むつ市政記者会、高知県政記者クラブ、沖縄県政記者クラブ、名護市駐在3社、兵庫県教育委員会記者クラブ、神戸民放記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ、環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会、立川市政記者クラブ同時配付)
-
2021年12月15日
 サーキュラーエコノミーを
サーキュラーエコノミーを
脱炭素化につなげるための必須条件を解明(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学記者会、科学記者会、大学記者会同時配付) -
2021年12月14日
 衛星観測が捉えた南米亜熱帯地域のメタン放出量と気象の関係 ~温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」によるメタン推定値と降水データの解析~(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学記者会、科学記者会同時配付)
衛星観測が捉えた南米亜熱帯地域のメタン放出量と気象の関係 ~温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」によるメタン推定値と降水データの解析~(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学記者会、科学記者会同時配付)
-
2021年12月10日
 2020年度(令和2年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について<環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会同時発表>
2020年度(令和2年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について<環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会同時発表>
-
2021年12月9日
 温暖化による稚樹の分布変化を検出
温暖化による稚樹の分布変化を検出
~森林タイプによる変化の違いが明らかに~(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付) -
2021年11月9日
 大気観測が捉えた新型ウィルスによる
大気観測が捉えた新型ウィルスによる
中国の二酸化炭素放出量の変動
~ロックダウン解除後は前年レベルに~(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学記者会、科学記者会同時配付) -
2021年10月7日
 真鍋先生のノーベル物理学賞受賞をお喜びします
真鍋先生のノーベル物理学賞受賞をお喜びします
-
2021年8月10日
 将来の不確実性を考慮に入れた飢餓リスクとその対応策の算定
将来の不確実性を考慮に入れた飢餓リスクとその対応策の算定
(京都大学記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会、草津市政記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ、農政クラブ、農林記者会、農業技術クラブ、筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付) -
2021年7月30日
 北海道大雪山の永久凍土を維持する環境が将来大幅に減少する(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、北海道教育庁記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会同時配付)
北海道大雪山の永久凍土を維持する環境が将来大幅に減少する(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、北海道教育庁記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会同時配付)
-
2021年7月28日
 AIと天気情報等の活用による熱中症発症数の高精度予測
AIと天気情報等の活用による熱中症発症数の高精度予測
- 熱中症発症数AI予測モデル開発の成功(大阪科学・大学記者クラブ、環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会) -
2021年7月20日
 大気汚染物質(NO2)との同時観測により燃焼由来のCO2排出量を精度よく推定する新手法を開発(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会文部科学記者会、科学記者会、その他JAXA配布先同時配布)
大気汚染物質(NO2)との同時観測により燃焼由来のCO2排出量を精度よく推定する新手法を開発(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会文部科学記者会、科学記者会、その他JAXA配布先同時配布)
-
2021年7月20日
 「アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ第18回会合(WGIA18)」
「アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ第18回会合(WGIA18)」
の結果について(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ同時配付) -
2021年7月19日
 国内52都市における脱炭素型
国内52都市における脱炭素型
ライフスタイルの効果を定量化
~「カーボンフットプリント」からみた移動・住居・食・レジャー・消費財利用の転換による脱炭素社会への道筋~(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配布) -
2021年7月15日
 東南アジアの泥炭・森林火災が
東南アジアの泥炭・森林火災が
日本の年間放出量に匹敵するCO2をわずか2か月間で放出
:旅客機と貨物船による観測が捉えたCO2放出(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、気象庁記者クラブ同時配布) -
2021年7月6日
 水資源の制約が
水資源の制約が
世界規模でのバイオエネルギー生産にもたらす影響を推定(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学記者会、科学記者会、京都大学記者クラブ、草津市政記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ同時配布) -
2021年6月29日
 地球温暖化予測において
地球温暖化予測において
雲減少による温暖化の加速効果が過小評価
-対流活動に着目して予測の不確かさを減らす-(環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会、大学記者会(東京大学)、文部科学記者会、科学記者会同時配布) -
2021年6月28日
 統計的ダウンスケーリングによる詳細な日本の気候予測情報を公開
統計的ダウンスケーリングによる詳細な日本の気候予測情報を公開
~日本で初めて第6期結合モデル相互比較プロジェクト(CMIP6)に準拠~
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配布) -
2021年6月25日
 貨物船と旅客機の民間協力観測によりCO2の
貨物船と旅客機の民間協力観測によりCO2の
人工衛星観測データを評価する新手法を開発(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学記者会、科学記者会同時配布) -
2021年6月15日
 北海道沿岸域の温暖化・酸性化・貧酸素化影響が明らかに
北海道沿岸域の温暖化・酸性化・貧酸素化影響が明らかに
~水産対象種に対する深刻な影響回避には具体的な対策が必要~(北海道教育庁記者クラブ,筑波研究学園都市記者会,文部科学記者会,科学記者会,環境省記者クラブ,環境記者会,水産庁記者クラブ同時配布) -
2021年6月11日
 孫は祖父母が遭遇しないような
孫は祖父母が遭遇しないような
暑い日と大雨を何度経験するのか?
-極端な気象現象の変化に関する世代間不公平性と
その地域間不公平性の評価-(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、京都大学記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会、草津市政記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ同時配布) -
2021年6月4日
 炭素制約が世界規模での金属生産と
炭素制約が世界規模での金属生産と
利用にもたらす影響を推定(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配布) -
2021年5月29日
 将来シナリオに応じた温室効果ガス排出指標の柔軟な選択
将来シナリオに応じた温室効果ガス排出指標の柔軟な選択
パリ協定温度目標へ向かうための排出削減費用の観点から(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配布) -
2021年5月28日
 世界各国の2050年の温室効果ガス削減目標を国横断的に分析するためのシナリオフレームワークの提案(京都大学記者クラブ、大学記者会(東京大学)、文部科学記者会、科学記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会同時配布)
世界各国の2050年の温室効果ガス削減目標を国横断的に分析するためのシナリオフレームワークの提案(京都大学記者クラブ、大学記者会(東京大学)、文部科学記者会、科学記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会同時配布)
-
2021年5月6日
 2019~2020年のオーストラリアの森林火災は
2019~2020年のオーストラリアの森林火災は
過去20年で同国において
最も多くの火災起源の二酸化炭素を放出した(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配布) -
2021年4月19日
 2019年度(令和元年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について(環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会同時発表)
2019年度(令和元年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について(環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会同時発表)
-
2021年1月29日
 過去30年間のメタンの大気中濃度と放出量の変化
過去30年間のメタンの大気中濃度と放出量の変化
:化石燃料採掘と畜産業による人間活動が増加の原因に
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、千葉県政記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会同時配布) -
2021年1月22日
 気候変動下で増加する洪水に、
気候変動下で増加する洪水に、
ダムでの洪水調節が及ぼす影響を世界で初めて推定(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、大学記者会(東京大学)、文部科学記者会、科学記者会同時配布) -
2021年1月14日
 過去の人間活動がもたらす日本南方沖の夏季異常高温
過去の人間活動がもたらす日本南方沖の夏季異常高温
~2020年8月の記録的北西太平洋高温の要因を分析~(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学記者会、科学記者会同時配布) -
2020年12月10日
 原子力技術を活用した温暖化対応研究をアジア諸国と協力して推進 -アジア原子力協力フォーラム大臣級会合において最優秀研究チーム賞を受賞-
原子力技術を活用した温暖化対応研究をアジア諸国と協力して推進 -アジア原子力協力フォーラム大臣級会合において最優秀研究チーム賞を受賞-
(日本原子力研究開発機構のサイトに掲載) -
2020年12月8日
 2019年度(令和元年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について<環境省・国立環境研究所 同時発表>
2019年度(令和元年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について<環境省・国立環境研究所 同時発表>
-
2020年11月17日
 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)のプロキシ法によるメタン濃度推定の誤差補正
温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)のプロキシ法によるメタン濃度推定の誤差補正
~10年間の観測データの解析~(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配布) -
2020年11月12日
 温室効果ガス観測技術衛星2号「いぶき2号」(GOSAT-2)による観測データの解析結果(二酸化炭素、メタン、一酸化炭素)と一般提供開始について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配布)
温室効果ガス観測技術衛星2号「いぶき2号」(GOSAT-2)による観測データの解析結果(二酸化炭素、メタン、一酸化炭素)と一般提供開始について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配布)
-
2020年10月20日
 地球温暖化が近年の日本の豪雨に与えた影響を評価しました(気象庁記者クラブ、環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会同時配布)
地球温暖化が近年の日本の豪雨に与えた影響を評価しました(気象庁記者クラブ、環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会同時配布)
-
2020年9月17日
 温暖化による全球乾燥度の変化と人為起源の影響を分析
温暖化による全球乾燥度の変化と人為起源の影響を分析
~世界の平均気温の上昇を1.5℃に抑えることで、乾燥化を大幅に抑制可能~(環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会同時配布) -
2020年8月28日
 エルニーニョ現象の緻密な再現が熱帯域の温暖化予測精度を向上させる
エルニーニョ現象の緻密な再現が熱帯域の温暖化予測精度を向上させる
—赤道太平洋の海面下数百メートルの海流変動が鍵—(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付) -
2020年8月3日
 「アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ第18回会合(WGIA18)」の中止と「温室効果ガスインベントリ相互学習」の結果について
「アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ第18回会合(WGIA18)」の中止と「温室効果ガスインベントリ相互学習」の結果について
(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ同時配付) -
2020年6月5日
 中国からのブラックカーボン排出量は過去10年で4割もの大幅減少
中国からのブラックカーボン排出量は過去10年で4割もの大幅減少
—IPCC気候モデルへの排出量入力値に見直しが必要—(文部科学記者会、科学記者会、神奈川県政記者クラブ、横須賀市政記者クラブ、青森県政記者会、むつ市政記者会、高知県政記者クラブ、沖縄県政記者クラブ、名護市駐在3社、兵庫県教育委員会記者クラブ、神戸民放記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ、環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会同時配付) -
2020年5月15日
 民間旅客機が捉えた都市域からのCO2排出
民間旅客機が捉えた都市域からのCO2排出
~世界34都市上空でのCO2観測データの統計解析~(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、気象庁記者クラブ同時配付) -
2020年4月14日
 2018年度(平成30年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ 同日発表)
2018年度(平成30年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ 同日発表)
-
2019年12月24日
 生物多様性保全のための科学的根拠を集約
生物多様性保全のための科学的根拠を集約
科学誌サイエンスに総説掲載(千葉大学のサイトに掲載) -
2019年12月12日
 地球温暖化対策を話し合う国連の会議「COP25」からのたより(その4)
地球温暖化対策を話し合う国連の会議「COP25」からのたより(その4)
-
2019年12月12日
 CO₂の放出と吸収のより正確な推定に成功
CO₂の放出と吸収のより正確な推定に成功
~IPCC第5次評価報告書からの進展と第6次評価報告書に向けた課題~(環境省記者クラブ、環境記者会、千葉県政記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会、筑波研究学園都市記者会、気象庁記者クラブ同時配付) -
2019年12月6日
 地球温暖化対策を話し合う国連の会議「COP25」からのたより(その3)
地球温暖化対策を話し合う国連の会議「COP25」からのたより(その3)
-
2019年12月6日
 地球温暖化対策を話し合う国連の会議「COP25」からのたより(その2)
地球温暖化対策を話し合う国連の会議「COP25」からのたより(その2)
-
2019年12月5日
 地球温暖化対策を話し合う国連の会議「COP25」からのたより(その1)
地球温暖化対策を話し合う国連の会議「COP25」からのたより(その1)
-
2019年12月3日
 生物多様性保全と温暖化対策は両立できる
生物多様性保全と温暖化対策は両立できる
-生物多様性の損失は気候安定化の努力で抑えられる-(林政記者クラブ、農林記者会、農政クラブ、筑波研究学園都市記者会、京都大学記者クラブ、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付) -
2019年11月29日
 2018年度(平成30年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について
2018年度(平成30年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について
-
2019年9月26日
 複数分野にわたる世界全体での地球温暖化による経済的被害を推計-温室効果ガス排出削減と社会状況の改善は被害軽減に有効-(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、茨城県政記者クラブ、京都大学記者クラブ、文部科学省記者会、科学記者会、大学記者会(東京大学)、農政クラブ、農林記者会、農業技術クラブ、草津市政記者クラブ 同時配付)
複数分野にわたる世界全体での地球温暖化による経済的被害を推計-温室効果ガス排出削減と社会状況の改善は被害軽減に有効-(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、茨城県政記者クラブ、京都大学記者クラブ、文部科学省記者会、科学記者会、大学記者会(東京大学)、農政クラブ、農林記者会、農業技術クラブ、草津市政記者クラブ 同時配付)
-
2019年9月13日
 地球温暖化によって熱帯域の積乱雲群は小規模化
地球温暖化によって熱帯域の積乱雲群は小規模化
~雲が温暖化をより進行させる可能性~
(配付先:文部科学記者会、科学記者会、大学記者会(東京大学)、神奈川県政記者クラブ、横須賀市政記者クラブ、青森県政記者会、むつ市政記者会、高知県政記者クラブ、沖縄県政記者クラブ、名護市駐在3社、筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ) -
2019年8月8日
 「アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ 第17回会合(WGIA17)」の結果について
「アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ 第17回会合(WGIA17)」の結果について
(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ同時配付) -
2019年7月5日
 温室効果ガス観測技術衛星2号「いぶき2号」(GOSAT-2)の観測データのプロキシ法による解析結果(メタンと一酸化炭素)について(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ同時配付)
温室効果ガス観測技術衛星2号「いぶき2号」(GOSAT-2)の観測データのプロキシ法による解析結果(メタンと一酸化炭素)について(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ同時配付)
-
2019年6月17日
 東アジアのメタン放出分布をボトムアップ手法で詳細にマップ化(お知らせ)
東アジアのメタン放出分布をボトムアップ手法で詳細にマップ化(お知らせ)
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会同時配付) -
2019年5月28日
 間伐が富士北麓カラマツ人工林林床の二酸化炭素収支におよぼす影響を網羅的に評価
間伐が富士北麓カラマツ人工林林床の二酸化炭素収支におよぼす影響を網羅的に評価
-撹乱に対する森林の炭素収支の回復力-
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会 同時配付) -
2019年5月22日
 平成30年7月の記録的な猛暑に地球温暖化が与えた影響と猛暑発生の将来見通し(気象庁記者クラブ、筑波研究学園都市記者会、文部科学記者会、大学記者会(東京大学)、科学記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配布)
平成30年7月の記録的な猛暑に地球温暖化が与えた影響と猛暑発生の将来見通し(気象庁記者クラブ、筑波研究学園都市記者会、文部科学記者会、大学記者会(東京大学)、科学記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配布)
-
2019年4月16日
 2017年度(平成29年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ 同日発表)
2017年度(平成29年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ 同日発表)
-
2019年4月2日
 世界の平均気温の上昇を1.5℃に抑えたときと2.0℃に抑えたときの影響を比較
~パリ協定の目標達成で、洪水と渇水が続いて起こるリスクを大幅に低減~
世界の平均気温の上昇を1.5℃に抑えたときと2.0℃に抑えたときの影響を比較
~パリ協定の目標達成で、洪水と渇水が続いて起こるリスクを大幅に低減~
-
2019年3月19日
 WMO温室効果ガス世界資料センターにおいて温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」データの提供を開始しました
<環境省、気象庁、国立環境研究所、宇宙航空研究開発機構同時発表>
WMO温室効果ガス世界資料センターにおいて温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」データの提供を開始しました
<環境省、気象庁、国立環境研究所、宇宙航空研究開発機構同時発表>
-
2019年2月28日
 帯広市で国立環境研究所地球環境セミナーを開催しました
帯広市で国立環境研究所地球環境セミナーを開催しました
-
2019年2月28日
 気候変動による影響の連鎖の可視化に成功
気候変動による影響の連鎖の可視化に成功
ー地球温暖化問題の全体像を人々が理解することに貢献ー(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学記者会、科学記者会、農政クラブ、農林記者会、農業技術クラブ同時配布) -
2019年2月19日
 平成30年度地球温暖化防止パネル展で地球環境研究センターのパネルを展示しました
平成30年度地球温暖化防止パネル展で地球環境研究センターのパネルを展示しました
-
2018年12月17日
 地球温暖化による穀物生産被害は
地球温暖化による穀物生産被害は
過去30年間で平均すると
世界全体で年間424億ドルと推定(資料修正) -
2018年12月11日
 地球温暖化による穀物生産被害は
地球温暖化による穀物生産被害は
過去30年間で平均すると
世界全体で年間424億ドルと推定(筑波研究学園都市記者会、農政クラブ、農林記者会、農業技術クラブ、環境省記者クラブ、環境記者会、気象庁記者クラブ同時配付) -
2018年11月30日
 2017年度(平成29年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について
2017年度(平成29年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について
-
2018年11月21日
 地球温暖化への適応策として屋外労働の時間帯変更の効果を推計-増大する暑熱ストレスに対して時間帯変更のみの効果は限定的-(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、京都大学記者クラブ同時配付)
地球温暖化への適応策として屋外労働の時間帯変更の効果を推計-増大する暑熱ストレスに対して時間帯変更のみの効果は限定的-(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、京都大学記者クラブ同時配付)
-
2018年11月20日
 地球温暖化は多様な災害の増加と同時発生をもたらし世界の多くの人に影響を与える(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学省記者会、科学記者会同時配信)
地球温暖化は多様な災害の増加と同時発生をもたらし世界の多くの人に影響を与える(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学省記者会、科学記者会同時配信)
-
2018年10月30日
 温室効果ガス観測技術衛星2号「いぶき2号」(GOSAT-2)の打上げとクリティカル運用期間の終了について
(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ同時配付)
温室効果ガス観測技術衛星2号「いぶき2号」(GOSAT-2)の打上げとクリティカル運用期間の終了について
(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ同時配付)
-
2018年10月23日
 「アジア地域におけるチャンバー観測ネットワークの活用による森林土壌CO2フラックスの定量的評価 平成27~29年度」
「アジア地域におけるチャンバー観測ネットワークの活用による森林土壌CO2フラックスの定量的評価 平成27~29年度」
国立環境研究所研究プロジェクト報告の刊行について(お知らせ)
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付) -
2018年10月4日
 「和風スマートシティづくりを目指して」
「和風スマートシティづくりを目指して」
国立環境研究所「環境儀」第70号の刊行について(お知らせ)(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ同時配付) -
2018年9月18日
 下層雲が繋ぐ温暖化時の気温と降水量の変化
下層雲が繋ぐ温暖化時の気温と降水量の変化
-
2018年7月31日
 温室効果ガス排出削減策が食料安全保障に及ぼす影響の評価(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、京都大学記者クラブ同時配付)
温室効果ガス排出削減策が食料安全保障に及ぼす影響の評価(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、京都大学記者クラブ同時配付)
-
2018年7月19日
 「アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ第16回会合(WGIA16)」の結果について
「アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ第16回会合(WGIA16)」の結果について
(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ同時配付) -
2018年4月24日
 2016年度(平成28年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ 同日発表)
2016年度(平成28年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ 同日発表)
-
2018年4月16日
 白神山地でも温暖化によって土壌から排出される二酸化炭素が増加-長期の疑似温暖化実験で土壌有機物の分解が促進される-
白神山地でも温暖化によって土壌から排出される二酸化炭素が増加-長期の疑似温暖化実験で土壌有機物の分解が促進される-
【お知らせ】(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、弘前記者会同時配付) -
2018年3月27日
 Reconciling Paris Agreement goals for temperature, emissions
Reconciling Paris Agreement goals for temperature, emissions
New study finds two targets don’t always go hand in hand
パリ協定の温度目標とゼロ排出目標の整合性
2つの目標は必ずしも一致しないことが明らかに(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付) -
2018年1月9日
 2016年度(平成28年度)の温室効果ガス排出量(速報値)の修正について<国立環境研究所 同日発表>
2016年度(平成28年度)の温室効果ガス排出量(速報値)の修正について<国立環境研究所 同日発表>
-
2017年12月13日
 欧州宇宙機関(ESA)、フランス国立宇宙研究センター(CNES)及びドイツ航空宇宙センター(DLR)との温室効果ガスのリモートセンシング及び関連ミッションに関する協定の締結について
欧州宇宙機関(ESA)、フランス国立宇宙研究センター(CNES)及びドイツ航空宇宙センター(DLR)との温室効果ガスのリモートセンシング及び関連ミッションに関する協定の締結について
-
2017年12月12日
 2016年度(平成28年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について<国立環境研究所 同日発表>
2016年度(平成28年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について<国立環境研究所 同日発表>
-
2017年11月21日

西シベリア上空のメタン濃度は高度によって上昇度に差異があると判明(筑波研究学園都市記者会、環境省記者会、環境省記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会、宮城県政記者会同時配布) -
2017年9月26日
 地球環境研究センターニュース2017年10月号「永久凍土は地球温暖化で解けているのか? アラスカ調査レポート」発行
地球環境研究センターニュース2017年10月号「永久凍土は地球温暖化で解けているのか? アラスカ調査レポート」発行
-
2017年8月28日
 温暖化の進行で世界の穀物収量の伸びは鈍化する
温暖化の進行で世界の穀物収量の伸びは鈍化する
-新たな将来予測の結果、世界の増加する食料需要を満たすためには、気候変動に適応した穀物生産技術がますます重要に-(筑波研究学園都市記者会、農政クラブ、農林記者会、農業技術クラブ、環境省記者クラブ同時配付) -
2017年8月10日
 地球環境研究センターニュース2017年9月号「進展を続ける宇宙からの観測—第13回宇宙からの温室効果ガス観測に関する国際ワークショップ(IWGGMS-13)参加報告—」発行
地球環境研究センターニュース2017年9月号「進展を続ける宇宙からの観測—第13回宇宙からの温室効果ガス観測に関する国際ワークショップ(IWGGMS-13)参加報告—」発行
-
2017年7月27日

東京スカイツリー(R)で大気中二酸化炭素(CO2)などの
温室効果ガス観測をはじめました(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、経済産業記者会、経済産業省ペンクラブ、中小企業庁ペンクラブ、資源記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会、東京大学記者会同時配付) -
2017年7月13日
 春の環境講座で行われたパネルディスカッション「ここが知りたい地球温暖化の適応策」の動画を公開しました
春の環境講座で行われたパネルディスカッション「ここが知りたい地球温暖化の適応策」の動画を公開しました
-
2017年6月12日
 地球温暖化によって追加的に必要となる
地球温暖化によって追加的に必要となる
労働者の熱中症予防の経済的コストを推計
(お知らせ)
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配付) -
2017年6月2日
 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)の観測データに基づくメタンの全大気平均濃度データの公開について
温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)の観測データに基づくメタンの全大気平均濃度データの公開について
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配付) -
2017年4月13日
 2015年度(平成27年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ 同日発表)
2015年度(平成27年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ 同日発表)
-
2017年2月9日
 「環境都市システム研究プログラム」
「環境都市システム研究プログラム」
国立環境研究所研究プロジェクト報告の刊行について
(お知らせ)
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配付) -
2017年2月2日
 「地球温暖化研究プログラム」
「地球温暖化研究プログラム」
国立環境研究所研究プロジェクト報告の刊行について
(お知らせ)
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配付) -
2017年1月12日
 「『世界の屋根』から地球温暖化を探る ~青海・チベット草原の炭素収支~」
「『世界の屋根』から地球温暖化を探る ~青海・チベット草原の炭素収支~」
国立環境研究所「環境儀」第63号の刊行について(お知らせ)(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配付) -
2016年12月6日
 2015年度(平成27年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同日発表)
2015年度(平成27年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同日発表)
-
2016年12月1日
 インド・デリー周辺の冬小麦が都市排出を上回る二酸化炭素を吸収
インド・デリー周辺の冬小麦が都市排出を上回る二酸化炭素を吸収
~民間航空機観測(CONTRAIL)から明らかになった新たな炭素吸収~(お知らせ)
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、気象庁記者クラブ同時配付) -
2016年10月27日
 季節変動を取り除いた全大気平均二酸化炭素濃度が初めて400 ppmを超えました!
季節変動を取り除いた全大気平均二酸化炭素濃度が初めて400 ppmを超えました!
~温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)による観測速報~
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配付) -
2016年10月24日
 JAXA筑波宇宙センター特別公開に「いぶき」チームが出展しました
JAXA筑波宇宙センター特別公開に「いぶき」チームが出展しました
-
2016年10月24日
 長期的な温暖化が土壌有機炭素分解による二酸化炭素排出量を増加させることを実験的に検証-6年間におよぶ温暖化操作実験による研究成果-
長期的な温暖化が土壌有機炭素分解による二酸化炭素排出量を増加させることを実験的に検証-6年間におよぶ温暖化操作実験による研究成果-
【お知らせ】
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配付) -
2016年10月6日
 「地球環境100年モニタリング ~波照間と落石岬での大気質監視~」国立環境研究所「環境儀」第62号の刊行について(お知らせ)
「地球環境100年モニタリング ~波照間と落石岬での大気質監視~」国立環境研究所「環境儀」第62号の刊行について(お知らせ)
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配付) -
2016年9月23日
 2013年夏季の東北アジア上空の大幅なメタン高濃度の原因を解明
2013年夏季の東北アジア上空の大幅なメタン高濃度の原因を解明
-温室効果ガス観測技術衛星GOSAT(「いぶき」)の観測能力の高さを実証-
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配付) -
2016年9月1日
 「いぶき」(GOSAT)観測データによる
「いぶき」(GOSAT)観測データによる
大都市等の人為起源二酸化炭素濃度の推定結果について
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配付) -
2016年7月7日
 「『適応』で拓く新時代! ~気候変動による影響に備える~」国立環境研究所「環境儀」第61号の刊行について(お知らせ)
「『適応』で拓く新時代! ~気候変動による影響に備える~」国立環境研究所「環境儀」第61号の刊行について(お知らせ)
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配付) -
2016年5月24日
 今世紀中に起こりうる気候変化由来の冷暖房需要の変化に起因する経済影響を解明(お知らせ)(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配布)
今世紀中に起こりうる気候変化由来の冷暖房需要の変化に起因する経済影響を解明(お知らせ)(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配布)
-
2016年5月20日
 全大気平均二酸化炭素濃度が初めて400 ppmを超えました
全大気平均二酸化炭素濃度が初めて400 ppmを超えました
~温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)による観測速報~
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、文部科学省記者クラブ同時配付) -
2016年5月2日
 つくばエキスポセンターに国立環境研究所の展示が登場! ~5月は、ココが知りたい!地球温暖化の今とこれから~ 【終了しました】
つくばエキスポセンターに国立環境研究所の展示が登場! ~5月は、ココが知りたい!地球温暖化の今とこれから~ 【終了しました】
-
2016年4月15日
 2014年度(平成26年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ 同日発表)
2014年度(平成26年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ 同日発表)
-
2016年2月26日
 国立環境研究所、長野県と基本協定を結び、来年度から高山帯の温暖化影響モニタリングを強化
国立環境研究所、長野県と基本協定を結び、来年度から高山帯の温暖化影響モニタリングを強化
-
2016年2月15日
 高山帯モニタリングに係る長野県と
高山帯モニタリングに係る長野県と
国立環境研究所との基本協定締結式のお知らせ【開催終了】
(筑波研究学園都市記者会配付) -
2016年2月1日
 大気化学輸送モデルを用いた新たな手法により地域別のメタン放出量を推定~熱帯域、東アジアの放出量に従来推定と異なる結果~(筑波研究学園都市記者会,文部科学記者会、科学記者会、神奈川県政記者クラブ、横須賀市政記者クラブ、青森県政
記者会、むつ市政記者会、高知県政記者クラブ、沖縄県政記者クラブ、名護市駐在3社同時配布)
大気化学輸送モデルを用いた新たな手法により地域別のメタン放出量を推定~熱帯域、東アジアの放出量に従来推定と異なる結果~(筑波研究学園都市記者会,文部科学記者会、科学記者会、神奈川県政記者クラブ、横須賀市政記者クラブ、青森県政
記者会、むつ市政記者会、高知県政記者クラブ、沖縄県政記者クラブ、名護市駐在3社同時配布)
-
2016年1月11日
 2090年代の世界平均気温変化予測の不確実性を、
2090年代の世界平均気温変化予測の不確実性を、
2050年までに大幅に低減できることを解明(お知らせ)
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配布) -
2015年12月8日
 バイオCCSなどの二酸化炭素除去技術にはまだ多くの制約があることが国際共同研究により判明
バイオCCSなどの二酸化炭素除去技術にはまだ多くの制約があることが国際共同研究により判明
-国際合意の2℃目標達成には、今すぐ積極的な排出削減が不可欠-(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配布) -
2015年11月27日
 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」
温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」
(GOSAT)によるメタン観測データと
人為起源排出量との関係について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、文部科学省記者クラブ同時配布) -
2015年11月26日
 2014年度(平成26年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配布)
2014年度(平成26年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配布)
-
2015年11月16日
 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)の観測データに基づく月別二酸化炭素の全大気平均濃度の公表について
温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)の観測データに基づく月別二酸化炭素の全大気平均濃度の公表について
(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、文部科学省記者クラブ同時配付) -
2015年9月18日
 森林の炭素貯留量を高精度に計測できる
森林の炭素貯留量を高精度に計測できる
衛星データ解析技術を開発(筑波研究学園都市記者会配付) -
2015年8月19日
 化石燃料燃焼による二酸化炭素排出量の全球1kmデータ(英語)を公開しました
化石燃料燃焼による二酸化炭素排出量の全球1kmデータ(英語)を公開しました
-
2015年7月17日
 地上・衛星観測データが示す大気中二酸化炭素
地上・衛星観測データが示す大気中二酸化炭素
の行方~異なる2つの最新手法を相互的に評価~(文部科学記者会、科学記者会、神奈川県政記者クラブ、横須賀市政記者クラブ、青森県政記者会、むつ市政記者会、高知県政記者クラブ、沖縄県政記者クラブ、名護市駐在3社、筑波研究学園都市記者会同時配付) -
2015年6月12日
 日食を利用して太陽光が大気中のオゾンへ与える影響を調査
日食を利用して太陽光が大気中のオゾンへ与える影響を調査
-
2015年5月19日
 「いぶき」に関するニュースレター 国立環境研究所 GOSAT PROJECT NEWSLETTER 2015年春季号(Issue#31)発行
「いぶき」に関するニュースレター 国立環境研究所 GOSAT PROJECT NEWSLETTER 2015年春季号(Issue#31)発行
-
2015年4月14日
 2013年度(平成25年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について(お知らせ)(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ 同時発表)
2013年度(平成25年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について(お知らせ)(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ 同時発表)
-
2015年1月13日
 SATテクノロジー・ショーケース 2015開催のお知らせ【終了しました】
SATテクノロジー・ショーケース 2015開催のお知らせ【終了しました】
-
2014年12月5日
 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)による大都市等における二酸化炭素観測データと人為起源排出量との関係について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、文科省記者クラブ同時配付)
温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)による大都市等における二酸化炭素観測データと人為起源排出量との関係について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、文科省記者クラブ同時配付)
-
2014年12月4日
 2013年度(平成25年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について(環境省記者クラブ、筑波研究学園都市記者会同時配布)
2013年度(平成25年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について(環境省記者クラブ、筑波研究学園都市記者会同時配布)
-
2014年11月25日
 気候変動枠組条約第20回締約国会議及び京都議定書第10回締約国会合(COP20/CMP10)におけるサイドイベント開催・ブース展示について(お知らせ)【終了しました】<筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配付>
気候変動枠組条約第20回締約国会議及び京都議定書第10回締約国会合(COP20/CMP10)におけるサイドイベント開催・ブース展示について(お知らせ)【終了しました】<筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配付>
-
2014年4月15日
 2012年度(平成24年度)の温室効果ガス排出量(確定値)について(お知らせ)(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ 同時発表)
2012年度(平成24年度)の温室効果ガス排出量(確定値)について(お知らせ)(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ 同時発表)
-
2014年3月27日
 「いぶき」(GOSAT)の観測データを用いた全球の月別メタン収支の推定結果について
「いぶき」(GOSAT)の観測データを用いた全球の月別メタン収支の推定結果について
-
2013年11月19日
 2012年度(平成24年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について(筑波研究学園都市記者会)
2012年度(平成24年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について(筑波研究学園都市記者会)
-
2013年10月31日
 気候変動枠組条約第19回締約国会議及び京都議定書第9回締約国会合(COP19/CMP9)におけるサイドイベント開催・ブース展示について(お知らせ)【終了しました】(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配付)
気候変動枠組条約第19回締約国会議及び京都議定書第9回締約国会合(COP19/CMP9)におけるサイドイベント開催・ブース展示について(お知らせ)【終了しました】(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配付)
-
2013年10月15日
 CGERリポート「日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2013年4月」を掲載
CGERリポート「日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2013年4月」を掲載
-
2013年10月15日
 CGERリポート「National Greenhouse Gas Inventory Report of JAPAN April, 2013」を掲載
CGERリポート「National Greenhouse Gas Inventory Report of JAPAN April, 2013」を掲載
-
2013年8月27日
 オンラインマガジン環環の8月号が公開されました
オンラインマガジン環環の8月号が公開されました
-
2013年7月16日
 「いぶき」に関するニュースレター 国立環境研究所 GOSAT PROJECT NEWSLETTER 2013年7月号(Issue#28)発行
「いぶき」に関するニュースレター 国立環境研究所 GOSAT PROJECT NEWSLETTER 2013年7月号(Issue#28)発行
-
2013年5月20日
 「アジア地域における温室効果ガスとエアロゾルによる排出インベントリ・モデリング・気候影響に関する国際ワークショップ」開催のお知らせ【終了しました】
「アジア地域における温室効果ガスとエアロゾルによる排出インベントリ・モデリング・気候影響に関する国際ワークショップ」開催のお知らせ【終了しました】
-
2013年3月13日
 9th International Workshop on Greenhouse Gas Measurements from Space(IWGGMS-9)のお知らせ【終了しました】
9th International Workshop on Greenhouse Gas Measurements from Space(IWGGMS-9)のお知らせ【終了しました】
-
2013年2月20日
 オンラインマガジン環環の2月号が公開されました
オンラインマガジン環環の2月号が公開されました
-
2012年12月5日
 2011年度(平成23年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ 同時発表)
2011年度(平成23年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ 同時発表)
-
2012年12月5日
 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)の観測データによる二酸化炭素吸収排出量等の推定結果の公開について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、宇宙航空研究開発機構 同時発表)
温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)の観測データによる二酸化炭素吸収排出量等の推定結果の公開について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、宇宙航空研究開発機構 同時発表)
-
2012年4月13日
 2010年度(平成22年度)の温室効果ガス排出量(確定値)について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ 同時配付)
2010年度(平成22年度)の温室効果ガス排出量(確定値)について(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ 同時配付)
-
2011年12月13日
 2010年度(平成22年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について(お知らせ)(環境省記者クラブ、筑波研究学園都市記者会 配付)
2010年度(平成22年度)の温室効果ガス排出量(速報値)について(お知らせ)(環境省記者クラブ、筑波研究学園都市記者会 配付)
-
2011年12月1日
 GOSATプロジェクトのウェブサイトにCOP17展示ブースでの配布資料を掲載
GOSATプロジェクトのウェブサイトにCOP17展示ブースでの配布資料を掲載
-
2011年11月29日
 CGERリポート「National Greenhouse Gas Inventory Report of JAPAN April, 2011」を発行
CGERリポート「National Greenhouse Gas Inventory Report of JAPAN April, 2011」を発行
-
2011年11月29日
 CGERリポート「日本国温室効果ガスインベントリ報告書2011年4月」を発行
CGERリポート「日本国温室効果ガスインベントリ報告書2011年4月」を発行
-
2011年10月28日
 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)による観測データを用いた全球の月別・地域別の二酸化炭素吸収排出量の推定について(お知らせ)(筑波研究学園都市記者会、環境省 記者クラブ、宇宙航空研究開発機構 同時発表)
温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)による観測データを用いた全球の月別・地域別の二酸化炭素吸収排出量の推定について(お知らせ)(筑波研究学園都市記者会、環境省 記者クラブ、宇宙航空研究開発機構 同時発表)
-
2011年8月12日
 国立環境研究所の研究情報誌「環境儀」第41号 「宇宙から地球の息吹を探る−炭素循環の解明を目指して」の刊行について(お知らせ)(筑波研究学園都市記者会、 環境省記者クラブ同時配付 )
国立環境研究所の研究情報誌「環境儀」第41号 「宇宙から地球の息吹を探る−炭素循環の解明を目指して」の刊行について(お知らせ)(筑波研究学園都市記者会、 環境省記者クラブ同時配付 )
-
2011年7月19日
 大型台風6号を「いぶき」が捉えました
大型台風6号を「いぶき」が捉えました
-
2011年6月14日
 南米チリの火山の噴煙がニュージーランドに到達した様子を「いぶき」が観測
南米チリの火山の噴煙がニュージーランドに到達した様子を「いぶき」が観測
-
2011年6月10日
 日本科学未来館「ジオ・コスモス」で「いぶき」のデータがご覧になれます
日本科学未来館「ジオ・コスモス」で「いぶき」のデータがご覧になれます
-
2011年4月26日
 2009年度(平成21年度)の温室効果ガス排出量(確定値)について(お知らせ)(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ 同時配付)
2009年度(平成21年度)の温室効果ガス排出量(確定値)について(お知らせ)(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ 同時配付)
関連記事
-
2023年3月28日
 国立環境研究所における
国立環境研究所における
「温室効果ガスに関する研究」の
あゆみ -
2023年2月28日
 グローバル・ストックテイクに向けた広域観測の必要性特集 温室効果ガスを「見る」ための科学
グローバル・ストックテイクに向けた広域観測の必要性特集 温室効果ガスを「見る」ための科学
-
2023年2月28日
 全量炭素カラム観測ネットワーク(TCCON)による温室効果ガスの気柱平均濃度の観測について特集 温室効果ガスを「見る」ための科学
全量炭素カラム観測ネットワーク(TCCON)による温室効果ガスの気柱平均濃度の観測について特集 温室効果ガスを「見る」ための科学
【研究ノート】 -
2023年2月28日
 人工衛星が観測するクロロフィル蛍光を利用した陸域植生CO2吸収量推定特集 温室効果ガスを「見る」ための科学
人工衛星が観測するクロロフィル蛍光を利用した陸域植生CO2吸収量推定特集 温室効果ガスを「見る」ための科学
【環境問題基礎知識】 -
2022年12月28日
 気候変動と生態系の関係 そのモニタリング特集 気候変動と生態系、モニタリング研究の今
気候変動と生態系の関係 そのモニタリング特集 気候変動と生態系、モニタリング研究の今
-
2022年12月28日
 気候変動の影響の評価と影響機構の解明特集 気候変動と生態系、モニタリング研究の今
気候変動の影響の評価と影響機構の解明特集 気候変動と生態系、モニタリング研究の今
【研究プログラムの紹介:「気候変動適応研究プログラム」から】 -
2022年12月27日
 ミニチュア大洋「日本海」が発する警告 海洋環境への地球温暖化の影響環境儀 No.86
ミニチュア大洋「日本海」が発する警告 海洋環境への地球温暖化の影響環境儀 No.86
-
2022年8月31日
 地域と共に創る持続可能な社会の実現特集 地域と共に創る持続可能な社会
地域と共に創る持続可能な社会の実現特集 地域と共に創る持続可能な社会
-
2022年8月31日
 人口減少と高齢化に伴う
人口減少と高齢化に伴う
使用済み紙おむつ排出量の推計特集 地域と共に創る持続可能な社会
【研究ノート】 -
2022年6月30日
 地球規模の気候影響予測特集 脱炭素社会に向けて大きく舵を切った世界
地球規模の気候影響予測特集 脱炭素社会に向けて大きく舵を切った世界
【環境問題基礎知識】 -
2022年6月30日
 大気汚染と気候の複合問題への挑戦 数値シミュレーションを用いた高解像度予測の最前線環境儀 No.85
大気汚染と気候の複合問題への挑戦 数値シミュレーションを用いた高解像度予測の最前線環境儀 No.85
-
2022年1月10日
 物質フロー革新研究プログラム始動特集 物質フロー革新研究プログラムPJ1
物質フロー革新研究プログラム始動特集 物質フロー革新研究プログラムPJ1
「物質フローの重要転換経路の探究と社会的順応策の設計」から
-
2021年12月28日
 草原との共生を目指して
草原との共生を目指して
~モンゴルにおける牧草地の脆弱性評価~環境儀 No.83 -
2021年12月28日
 モンゴルの草原と人々の生活を守るためにInterview研究者に聞く
モンゴルの草原と人々の生活を守るためにInterview研究者に聞く
-
2021年12月28日
 気候変動および人為的攪乱による
気候変動および人為的攪乱による
草原生態系への影響評価Summary -
2021年10月29日
 温室効果ガスや大気汚染物質の排出量を迅速に把握する重要性とその方法特集 温室効果ガスや大気汚染物質の排出実態を迅速に把握する
温室効果ガスや大気汚染物質の排出量を迅速に把握する重要性とその方法特集 温室効果ガスや大気汚染物質の排出実態を迅速に把握する
-
2021年10月29日
 大気観測はCOVID-19 感染拡大による二酸化炭素排出減少を捉えられるか?特集 温室効果ガスや大気汚染物質の排出実態を迅速に把握する
大気観測はCOVID-19 感染拡大による二酸化炭素排出減少を捉えられるか?特集 温室効果ガスや大気汚染物質の排出実態を迅速に把握する
【研究ノート】 -
2021年10月29日
 衛星リモートセンシングを用いた全球
衛星リモートセンシングを用いた全球
およびオーストラリアの森林火災による二酸化炭素
放出量の研究の紹介
特集 温室効果ガスや大気汚染物質の排出実態を迅速に把握する
【研究ノート】 -
2021年9月30日
 人が去ったそのあとに
人が去ったそのあとに
人口減少下における里山の生態系変化と
その管理に関する研究環境儀 No.82 -
2021年9月30日
 人口減少時代の里山の管理のあり方とはInterview研究者に聞く
人口減少時代の里山の管理のあり方とはInterview研究者に聞く
-
2021年8月31日
 「気候変動適応の推進に向けて」特集 不確実な未来への備えを科学する「気候変動適応」研究プログラム
「気候変動適応の推進に向けて」特集 不確実な未来への備えを科学する「気候変動適応」研究プログラム
-
2021年8月31日
 統計的ダウンスケーリングによる日本の
統計的ダウンスケーリングによる日本の
気候シナリオ特集 不確実な未来への備えを科学する「気候変動適応」研究プログラム
【研究ノート】 -
2021年8月31日
 「シミュレーション研究者、田んぼに行く!!」特集 不確実な未来への備えを科学する「気候変動適応」研究プログラム
「シミュレーション研究者、田んぼに行く!!」特集 不確実な未来への備えを科学する「気候変動適応」研究プログラム
【調査研究日誌】 -
2021年8月31日
 気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)特集 不確実な未来への備えを科学する「気候変動適応」研究プログラム
気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)特集 不確実な未来への備えを科学する「気候変動適応」研究プログラム
【研究施設・業務等の紹介】 -
2021年6月30日
 広く社会に貢献する環境研究の継承と展開
広く社会に貢献する環境研究の継承と展開
-
2021年6月30日
 持続可能な地球環境の実現に向けて【地球システム領域の紹介】
持続可能な地球環境の実現に向けて【地球システム領域の紹介】
-
2021年6月30日
 人と社会と環境-社会システム領域の概要【社会システム領域の紹介】
人と社会と環境-社会システム領域の概要【社会システム領域の紹介】
-
2021年6月29日
 気候変動から生き物を守る
気候変動から生き物を守る
自然生態系分野の適応研究環境儀 No.81 -
2021年6月29日
 生態系への気候変動の影響を探るInterview研究者に聞く
生態系への気候変動の影響を探るInterview研究者に聞く
-
2020年10月29日
 温室効果ガス収支のマルチスケール監視とモデル高度化に関する統合的研究
温室効果ガス収支のマルチスケール監視とモデル高度化に関する統合的研究
~温室効果ガスの吸収・排出源を訪ねて~特集 温室効果ガスや大気汚染物質の排出実態を迅速に把握する
【研究プログラムの紹介:「気候変動適応研究プログラム」から】 -
2020年8月28日
 パリ協定の進捗確認:
パリ協定の進捗確認:
温室効果ガス観測の新しい役割特集 マルチスケールGHG変動評価システム構築と緩和策評価
-
2020年2月26日
 国連気候変動枠組条約(UNFCCC)
国連気候変動枠組条約(UNFCCC)
第25回締約国会議(COP25)参加報告
【行事報告】 -
2018年12月27日
 GOSAT-2が無事打ち上げられました!【行事報告】
GOSAT-2が無事打ち上げられました!【行事報告】
-
2018年9月28日
 IoT時代の和風スマートシティの実現を目指すInterview研究者に聞く
IoT時代の和風スマートシティの実現を目指すInterview研究者に聞く
-
2018年9月28日
 東京オリンピック・パラリンピック時における熱中症対策コラム3
東京オリンピック・パラリンピック時における熱中症対策コラム3
-
2018年9月28日
 国立環境研究所における
国立環境研究所における
「GCP/都市モデルに関する研究」のあゆみ -
2018年8月31日
 将来の気候変動と人間活動の変化を予測する特集 地球規模の気候変動リスクに関するモデル研究
将来の気候変動と人間活動の変化を予測する特集 地球規模の気候変動リスクに関するモデル研究
【研究ノート】 -
2018年6月29日
 宇宙と地上から温室効果ガスを捉える
宇宙と地上から温室効果ガスを捉える
-太陽光による高精度観測への挑戦-環境儀 No.69 -
2018年6月29日
 宇宙から温室効果ガスを観測するInterview研究者に聞く
宇宙から温室効果ガスを観測するInterview研究者に聞く
-
2018年6月29日
 カラム量とカラム平均濃度
カラム量とカラム平均濃度
コラム2 -
2018年6月29日
 いぶきの観測手法についてコラム3
いぶきの観測手法についてコラム3
-
2018年6月29日
 分光リモートセンシングによる温室効果ガス観測の高精度化への挑戦Summary
分光リモートセンシングによる温室効果ガス観測の高精度化への挑戦Summary
-
2018年6月29日
 分光リモートセンシングによる温室効果ガスの観測研究をめぐって
分光リモートセンシングによる温室効果ガスの観測研究をめぐって
-
2018年6月29日
 国立環境研究所における
国立環境研究所における
「温室効果ガスの分光リモートセンシングに関する研究」のあゆみ -
2018年6月29日
 過去の環境儀から
過去の環境儀から
-
2018年6月29日
 「春の環境講座-地球のことでアタマをいっぱいにする1日。-」開催報告【行事報告】
「春の環境講座-地球のことでアタマをいっぱいにする1日。-」開催報告【行事報告】
-
2018年4月27日
 気候変動抑制の鍵は賢明な政策にあり!?(2018年度 37巻1号)特集 アジアと世界の持続性に向けて
気候変動抑制の鍵は賢明な政策にあり!?(2018年度 37巻1号)特集 アジアと世界の持続性に向けて
【研究ノート】 -
2018年2月28日
 国連気候変動枠組条約(UNFCCC)第23回締約国会議(COP23)
国連気候変動枠組条約(UNFCCC)第23回締約国会議(COP23)
京都議定書第13回締約国会合(CMP13)
パリ協定第1回締約国会合再開会合(CMA1-2)
参加報告
-
2017年9月29日
 土壌は温暖化を加速するのか?
土壌は温暖化を加速するのか?
アジアの森林土壌が握る膨大な炭素の将来環境儀 No.66 -
2017年9月29日
 過去の環境儀から
過去の環境儀から
-
2017年8月31日
 温室効果ガス排出量の削減の進捗を評価する-グローバルとローカルー特集 マルチスケール温室効果ガス観測
温室効果ガス排出量の削減の進捗を評価する-グローバルとローカルー特集 マルチスケール温室効果ガス観測
-
2017年8月31日
 マルチスケールGHG変動評価システム構築と緩和策評価に関する研究特集 マルチスケール温室効果ガス観測
マルチスケールGHG変動評価システム構築と緩和策評価に関する研究特集 マルチスケール温室効果ガス観測
【シリーズ研究プログラムの紹介:「低炭素研究プログラム」から】 -
2017年8月31日
 地球温暖化で土壌から排出される二酸化炭素の量がどれほど増えるのか特集 マルチスケール温室効果ガス観測
地球温暖化で土壌から排出される二酸化炭素の量がどれほど増えるのか特集 マルチスケール温室効果ガス観測
【研究ノート】 -
2017年4月28日
 地球規模の環境問題解決の「シナリオ」を描く特集 気候変動の緩和・適応から多様な環境問題の解決に向けて
地球規模の環境問題解決の「シナリオ」を描く特集 気候変動の緩和・適応から多様な環境問題の解決に向けて
【研究ノート】 -
2016年12月28日
 「世界の屋根」から地球温暖化を探る
「世界の屋根」から地球温暖化を探る
~青海・チベット草原の炭素収支~環境儀 No.63 -
2016年12月28日
 草原の炭素の動きを探るInterview研究者に聞く
草原の炭素の動きを探るInterview研究者に聞く
-
2016年12月28日
 青海・チベット草原から地球温暖化を探るSummary
青海・チベット草原から地球温暖化を探るSummary
-
2016年12月28日
 国立環境研究所における
国立環境研究所における
「東アジアの草原生態系に関する温暖化研究」の
これまでの研究プロジェクト
-
2016年9月30日
 地球環境100年モニタリング
地球環境100年モニタリング
~波照間と落石岬での大気質監視~環境儀 NO.62 -
2016年9月30日
 100年続けることをめざすInterview研究者に聞く
100年続けることをめざすInterview研究者に聞く
-
2016年9月30日
 濃度標準ガスの開発コラム1
濃度標準ガスの開発コラム1
-
2016年9月30日
 温室効果ガスの各国の発生量推移コラム2
温室効果ガスの各国の発生量推移コラム2
-
2016年9月30日
 温室効果ガスの長期的変動をモニタリングする事業Summary
温室効果ガスの長期的変動をモニタリングする事業Summary
-
2016年9月30日
 温室効果ガス観測の現状研究をめぐって
温室効果ガス観測の現状研究をめぐって
-
2016年9月30日
 地球環境モニタリングステーションのあゆみ
地球環境モニタリングステーションのあゆみ
-
2016年8月31日
 「ゼロ炭素」社会を目指す「低炭素」研究プログラム特集 パリ協定とその先を見据えて
「ゼロ炭素」社会を目指す「低炭素」研究プログラム特集 パリ協定とその先を見据えて
-
2016年8月31日
 気候変動対策と大気汚染対策の最適なバランスとは?特集 パリ協定とその先を見据えて
気候変動対策と大気汚染対策の最適なバランスとは?特集 パリ協定とその先を見据えて
【研究ノート】 -
2016年8月31日
 国立環境研究所公開シンポジウム 2016
国立環境研究所公開シンポジウム 2016
「守るべき未来と「環境」の今 ~地球・生物・循環・安全・社会の半歩先を語ろう~」開催報告【行事報告】 -
2016年6月30日
 「適応」で拓く新時代!
「適応」で拓く新時代!
~気候変動による影響に備える~環境儀 NO.61 -
2016年6月30日
 地球温暖化影響予測の前提条件(社会経済・排出・気候シナリオ)コラム3
地球温暖化影響予測の前提条件(社会経済・排出・気候シナリオ)コラム3
-
2016年6月30日
 国立環境研究所の
国立環境研究所の
気候変動影響評価に関する研究のあゆみ -
2016年6月30日
 過去の環境儀から
過去の環境儀から
-
2016年6月30日
 国環研の新たな挑戦
国環研の新たな挑戦
-
2016年6月30日
 地球環境問題と地球環境研究センター【地球環境研究センターの紹介】
地球環境問題と地球環境研究センター【地球環境研究センターの紹介】
-
2015年12月28日
 持続可能な発展と衡平性【環境問題基礎知識】
持続可能な発展と衡平性【環境問題基礎知識】
-
2015年10月30日
 地球規模で長期の気候変動リスクにどう向き合うか特集 地球規模で長期の気候変動リスク
地球規模で長期の気候変動リスクにどう向き合うか特集 地球規模で長期の気候変動リスク
-
2015年10月30日
 地球規模の気候変動リスクに対する人類の選択肢
— ICA-RUS プロジェクト報告書第一版より—特集 地球規模で長期の気候変動リスク
地球規模の気候変動リスクに対する人類の選択肢
— ICA-RUS プロジェクト報告書第一版より—特集 地球規模で長期の気候変動リスク
【シリーズ重点研究プログラムの紹介:「地球温暖化研究プログラム」から】 -
2015年4月30日
 都市ヒートアイランドとエネルギー消費特集 都市から進める環境イノベーション
都市ヒートアイランドとエネルギー消費特集 都市から進める環境イノベーション
【環境問題基礎知識】 -
2014年7月3日
 地球観測技術環境展望台「環境技術解説」
地球観測技術環境展望台「環境技術解説」
-
2014年4月30日
 炭素循環を観測する特集 炭素循環を観測する
炭素循環を観測する特集 炭素循環を観測する
-
2014年4月30日
 民間の旅客機を活用した二酸化炭素濃度の観測特集 炭素循環を観測する
民間の旅客機を活用した二酸化炭素濃度の観測特集 炭素循環を観測する
【シリーズ重点研究プログラムの紹介:「地球温暖化研究プログラム」から】 -
2014年4月30日
 宇宙からの温室効果ガスの高精度観測
-『いぶき』(GOSAT)プロジェクトの現状-特集 炭素循環を観測する
宇宙からの温室効果ガスの高精度観測
-『いぶき』(GOSAT)プロジェクトの現状-特集 炭素循環を観測する
【研究ノート】 -
2013年6月28日
 低炭素社会の実現に向けた実践的な研究を目指して【シリーズ重点研究プログラム:『地球温暖化研究プログラム』から】
低炭素社会の実現に向けた実践的な研究を目指して【シリーズ重点研究プログラム:『地球温暖化研究プログラム』から】
-
2011年8月31日
 温室効果ガス等の濃度変動特性の解明とその将来予測に関する研究【シリーズ重点研究プログラムの紹介: 「地球温暖化研究プログラム」 から】
温室効果ガス等の濃度変動特性の解明とその将来予測に関する研究【シリーズ重点研究プログラムの紹介: 「地球温暖化研究プログラム」 から】
-
2011年7月31日
 宇宙から地球の息吹を探る
宇宙から地球の息吹を探る
- 炭素循環の解明を目指して環境儀 NO.41 -
2011年7月31日
 研究者に聞く!!Interview
研究者に聞く!!Interview
-
2011年7月31日
 二酸化炭素の全球の吸収・排出量を地域ごとに推定するための研究Summary
二酸化炭素の全球の吸収・排出量を地域ごとに推定するための研究Summary
-
2011年7月31日
 衛星からの温室効果ガスの観測研究をめぐって
衛星からの温室効果ガスの観測研究をめぐって
-
2011年7月31日
 「国立環境研究所GOSATプロジェクト」に関する研究と事業のあゆみ
「国立環境研究所GOSATプロジェクト」に関する研究と事業のあゆみ
-
2011年6月30日
 国内外の地球環境政策立案に資する研究展開を【地球環境研究センターの紹介】
国内外の地球環境政策立案に資する研究展開を【地球環境研究センターの紹介】
関連研究報告書
-
 2017年2月2日地球温暖化研究プログラム(重点研究プログラム)
2017年2月2日地球温暖化研究プログラム(重点研究プログラム)
平成23~27年度国立環境研究所研究プロジェクト報告 SR-112-2016 -
 2015年10月29日MRI画像解析と同位体解析による栄養塩や温室効果ガスの底泥からのフラックス予測(分野横断型提案研究)
2015年10月29日MRI画像解析と同位体解析による栄養塩や温室効果ガスの底泥からのフラックス予測(分野横断型提案研究)
平成24~26年度国立環境研究所研究プロジェクト報告 SR-110-2015 -
 2011年12月28日地球温暖化研究プログラム(終了報告)
2011年12月28日地球温暖化研究プログラム(終了報告)
平成18〜22年度国立環境研究所特別研究報告 SR-96-2011 -
 2008年12月26日地球温暖化研究プログラム(中間報告)
2008年12月26日地球温暖化研究プログラム(中間報告)
平成18〜19年度国立環境研究所特別研究報告 SR-82-2008 -
 2003年9月30日大気汚染・温暖化関連物質監視のためのフーリエ変換赤外分光計測技術の開発に関する研究(革新的環境監視計測技術先導研究)
2003年9月30日大気汚染・温暖化関連物質監視のためのフーリエ変換赤外分光計測技術の開発に関する研究(革新的環境監視計測技術先導研究)
平成12〜14年度国立環境研究所特別研究報告 SR-52-2003